このイベントは盛況のうちに無事終了しました
内容についてご興味、ご質問のある方は、こちらからお問い合わせください
本セミナーは、MSIISM Conference 2025 での講演
「生成AIの再評価と数理科学」と同様の内容でお届けします
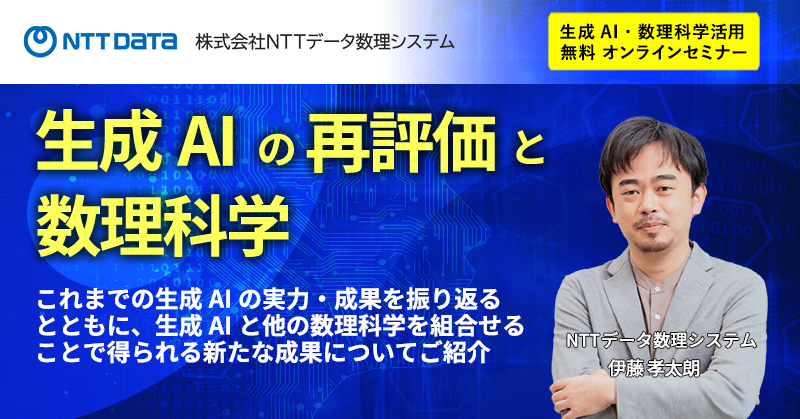
SUMMARYセミナー概要
生成AIは驚異的な進化を遂げ、企業の業務変革に大きな期待を集めました。一方で、直近の調査によると、AI投資により実際に利益向上を達成できた企業は100社中わずか5社という現状があります。また、現実には「何に使えるか」が不明確なまま導入が停滞する例も少なくありません。
本セミナーでは、この二極化の現状を整理するとともに、「生成AIの導入における重要なポイント」「生成AIと数理科学の組み合わせによって得られる価値」という観点から、成功する5社に入るためのヒントをお伝えします。
本セミナーは、MSIISM Conference 2025 での講演「生成AIの再評価と数理科学」と同様の内容でお届けします。コンファレンスに来られなかった方や、すでに講演を聞いていただいていて、もう一度聞きたい、周りの人にも聞いてもらいたいとお考えの方はこの機会にぜひお申し込みください。
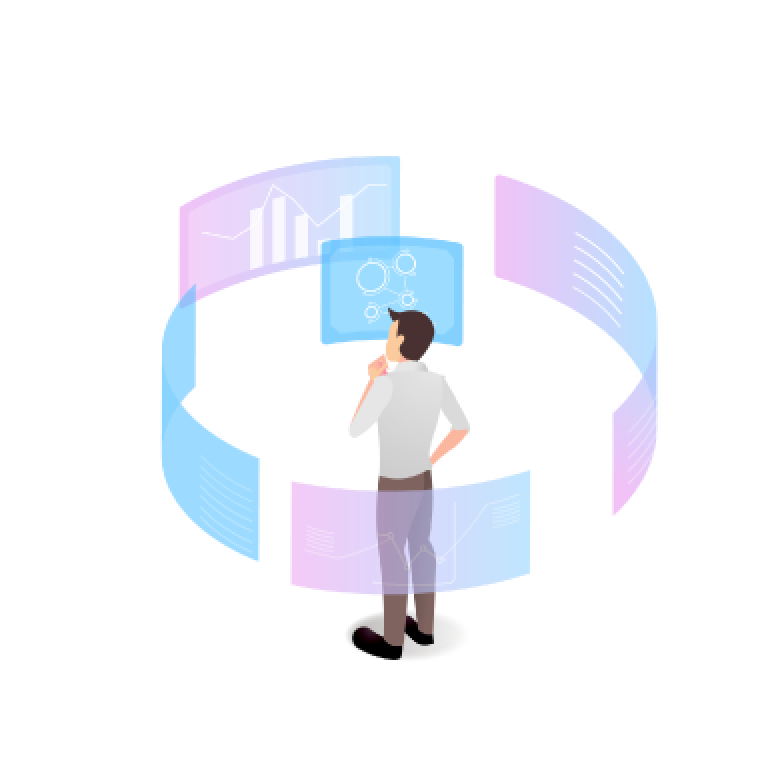
RECOMMENDこんな方におすすめ
-
生成AIの導入による効果検証(PoC)を実施したが、思った通りの成果が出なかった方
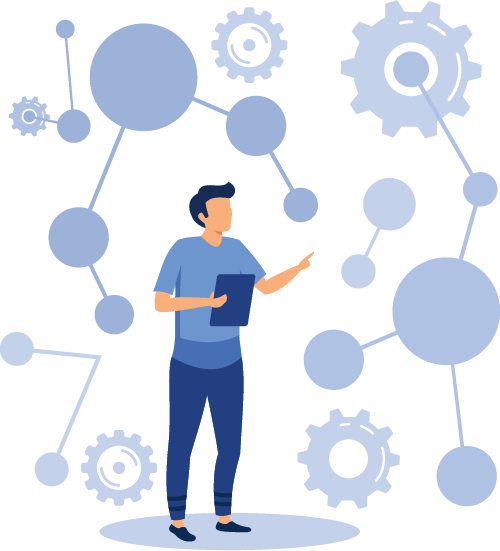
-
既に数理科学(機械学習・最適化・シミュレーション)ソリューションを導入していて、その価値を生成AIによってさらに高めたい方
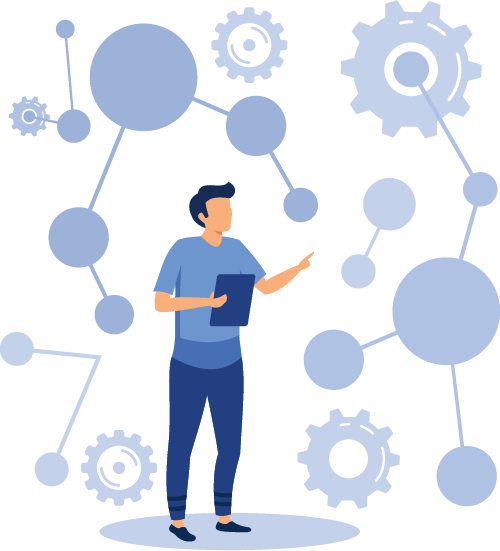
-
生成AIの導入を成功に導くプロジェクトの考え方を知りたい方
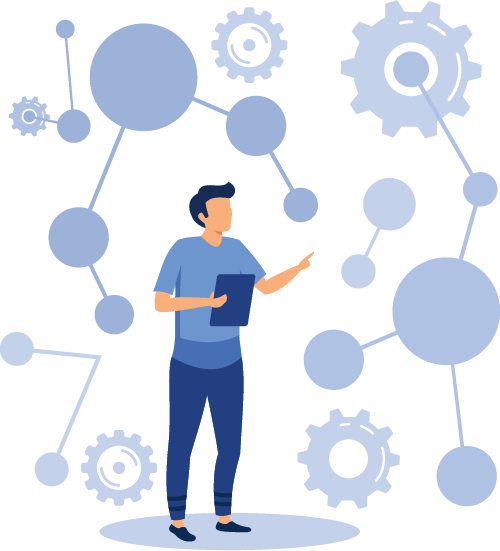
FEATURESセミナーでわかること
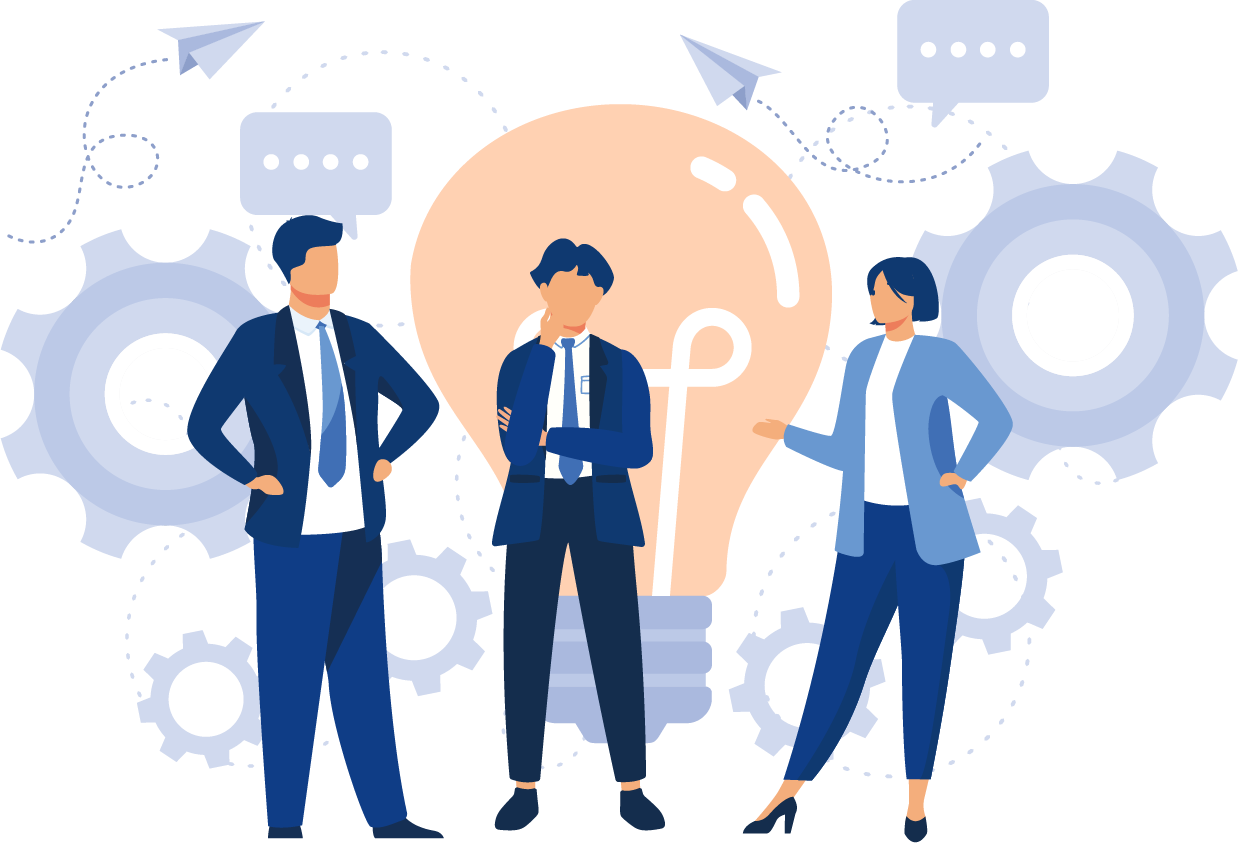
EVENT PROGRAM当日のプログラム
※ 新たに内容を追加させていただく可能性がございます
- プログラム1
-
生成AIの再評価
生成AIへの投資は増加していますが、実際に利益向上につながっている企業はわずか100社中5社という二極化の現状があります。本プログラムでは、2024年-2025年の生成AIの技術トレンドの調査結果をもとに、生成AIの活用方針についてお話します。
- プログラム2
-
数理科学の再評価
数理最適化やシミュレーションが直接意思決定につながる技術であることを説明し、生成AIと数理科学技術の差分や関係性を明らかにします。さらに、生成AIと数理科学を組み合わせることで得られる新たな価値についてもお伝えします。
- プログラム3
-
価値を出す側にまわるには
これまでお話した内容を踏まえ、生成AIを活用して利益向上につなげるための考え方についてお話します。二極化の壁を越え、5社側に入るためにはどうすればよいか、そのヒントを得ることができます。
SPEAKERS登壇者情報
-

株式会社NTTデータ数理システム
シミュレーション&マイニング部 マネージャー
生成AI推進室 マネージャー伊藤 孝太朗
データサイエンティストとして AI 活用プロジェクトを牽引し、当社の生成 AI 活用に関する取り組みを推進するチームのリーダーを務める。近年は生成 AI によるマルチエージェントモデルを活用したプロジェクトの PM を務めるなど、生成 AI 活用の最前線で活躍している
SCHEDULE開催日程
- イベント名
- 生成AIの再評価と数理科学
- 開催場所
- ウェビナーにて開催します。参加方法は申し込みページでご確認いただけます。
FOLLOW UPイベント後は技術スタッフへの
直接のご相談も可能です
-
イベントに参加したけど
よくわからない所があった
担当スタッフによる個別のフォローを行いますので、当社製品について不明な所があれば何でもお聞き下さい。
-
自社の課題を解決するための
具体的な方法が知りたい
解決したい課題をお聞かせいただければ過去の解決事例や、ソリューション・最適なツールのご紹介が可能です。
※不要な営業・ご提案は行いませんのでご安心下さい。 -
この分野の知識が無い、
でも解決したい課題がある
どんなお悩みでもぜひ一度お聞かせ下さい。課題の棚卸しや解決に必要な技術のご説明など、お客様のお困りごとの解決の一助となる内容をお伝えします。
ABOUT USNTTデータ数理システムについて
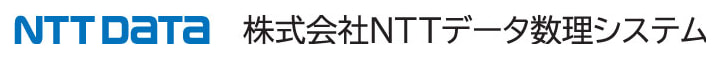

NTTデータ数理システムってどんな会社?
NTTデータ数理システムは「数理科学とコンピュータサイエンスにより現実世界の問題を解決する」をミッションとしている会社です。
1982年設立の会社で、大学で数学や物理を学んでも社会でその知識を発揮できる仕事ができないという人も多い時代から、数理科学的な知識を生かせる場を作りたいという理念で会社を発展させてきました。
ビッグデータブーム、AIブームを経て、今では機械学習を使うために数理科学的な素養のある人を雇いたいという会社も多くなりましたが、このような活動をしている会社としてはかなりの老舗です。
機械学習、統計解析、数理計画、シミュレーションなどの数理科学を背景とした技術を活用し、業種、テーマを問わず幅広く仕事をしています。
NTTデータ数理システムの得意な領域
昨今は AI という言葉で様々な技術領域を包含した表現します。当社でもセミナー等では抽象的に AI という言葉を用いた説明を行っています。実際の当社の開発現場では、要素技術を大切にしており理論的背景をおさえ、新旧横断的に活用してお客様へ価値提供しています。
- 機械学習全般(Deep Learning/強化学習/各種モデル)
- データマイニング/テキストマイニング/統計解析
- 数理最適化(厳密解法/近似解法/動的計画法)
- シミュレーション(物理/エージェント/待ち行列など)
などを活用しています。
